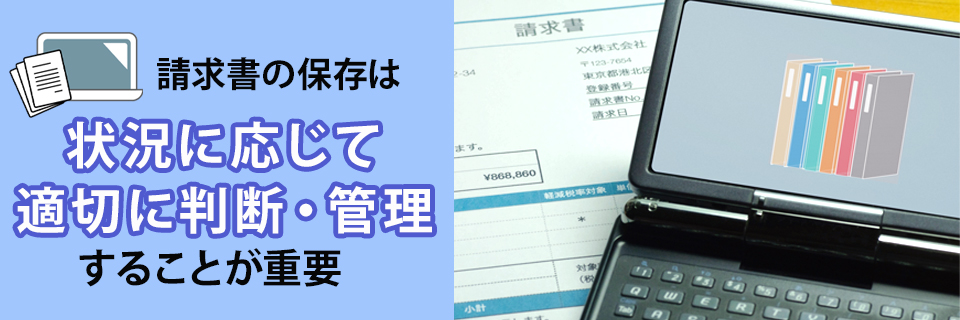コラム
電子帳簿保存法に沿ってメールで受け取った請求書を正しく保存する方法
請求書をメールで受け取る機会が増える中、「このデータをどのように保存すれば電子帳簿保存法に対応できるのか」と悩む経理・総務担当者は多いでしょう。紙の書類とは異なり、メールで受け取った請求書は「電子取引」として扱われるため、単に印刷して保管するだけでは法的要件を満たせません。
当記事では、電子帳簿保存法における電子取引の保存要件、メールで受け取った請求書の保存方法、注意点を分かりやすく解説します。法令に沿った正しい保存方法を理解すれば、自社の経理業務をスムーズかつ安心して行えるでしょう。
1. 電子帳簿保存法における電子取引の保存要件
電子帳簿保存法では、メールで受け取った請求書を含む電子取引データを保存する際、一定の要件を満たすことを求めています。ここでは、電子帳簿保存法で定められたデータ保存要件について詳しく解説します。
1-1. 真実性の確保
真実性の確保とは、電子データ保存において改ざんされていないことを証明するための要件です。紙の書類と異なり、電子データは編集や削除の痕跡が残りにくいため、信頼性を担保する仕組みが不可欠です。具体的には、次のいずれかの電子保存方法で要件を満たす必要があります。
- タイムスタンプが付与された電子データを受け取る
- 電子データの授受後、速やかにタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の履歴が残る、または編集できないシステムで電子データを授受・保存する
- 不当な訂正や削除を防ぐ事務処理規程を制定・運用する
メール本文を保存する場合はタイムスタンプ付与が難しいため、(3)や(4)による対応が現実的です。自社システムや専用サービスを活用し、これらの要件を確実に満たす運用体制を整えることが求められます。
1-2. 可視性の確保
可視性の確保とは、保存した電子データを必要なときにすぐに確認・出力できるようにするための要件です。たとえデータが保存されていても、内容を正確に確認できなければ適切な保存とは言えません。可視性を確保するには、以下の3点が必要です。
- 電子データを整然とした形式で画面表示・出力できる環境(パソコン・ディスプレイ・プリンター・操作マニュアル等)を備える
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付ける
- 検索機能を確保する
検索機能は「取引年月日・金額・取引先」で検索できることが基本要件で、複数項目の組み合わせ検索のほか、日付や金額は指定の範囲で条件を設定できることが望ましいとされています。ただし、税務職員のダウンロード要求に応じられる体制であれば、(2)(3)の要件は不要です。
2. メールで受け取った請求書の電子帳簿保存法に則った保存方法
メールで受け取った請求書を保存する場合、請求書が添付ファイルとして送られているのか、メール本文に取引情報が記載されているのかによって、電子帳簿保存法に沿った適切な保存方法が異なります。ここでは、それぞれのケースに応じた保存方法を解説します。
2-1. メールに請求書ファイルが添付されている場合
PDFなどの形で電子請求書がメールに添付されている場合は、電子帳簿保存法に沿った形で保存する必要があります。ここでは、添付ファイルを適切に管理・保存する方法を紹介します。
- 添付ファイルにタイムスタンプを付与して保存する
請求書が添付されたファイルを受け取ったら、ハードディスク・DVD・クラウドなどの別媒体に保存し、タイムスタンプ付与を行います。これにより、データが改ざんされていないことを証明でき、真実性の要件を満たせます。保存先のシステムにタイムスタンプ機能が備わっているかを事前に確認しておきましょう。 - 電帳法の要件を満たしたメールシステムで保存する
自社のメールシステムに、訂正・削除の履歴を確認できる、または削除ができない機能がある場合、そのままメールごと保存することで真実性を確保できます。メール本文と添付ファイルを一体で保管できるため、管理が容易です。ただし、システムが要件を満たしているかどうか、導入前に確認が必要です。 - あらかじめ用意した事務処理規程に沿って保存する
システム対応が難しい場合は、事務処理規程を作成し、その内容に従って保存する方法でも要件を満たせます。規程には、保存手順・担当者・確認方法などを明記し、実際の運用もルール通りに行うことが大切です。国税庁が公開しているサンプルを活用するとスムーズです。 - 索引簿を付けてデータを管理する
添付ファイルに連番を付け、請求書データの取引年月日・取引先・金額などの情報を索引簿に記録する方法です。検索要件を満たせる上、一覧で把握しやすいのが利点です。ただし、取引数が多い場合は記入漏れに注意し、定期的な更新管理を徹底しましょう。
2-2. メール本文に取引情報が記載されている場合
メール本文に請求内容や取引データが直接記載されている場合も、電子帳簿保存法の要件に沿って保存する必要があります。ここでは、要件を満たす代表的な方法を紹介します。
- 電帳法の要件を満たしたメールシステムで保存する
自社のメールシステムが電子帳簿保存法対応システムであり、訂正や削除の履歴を確認できる、または削除自体ができない機能がある場合は、そのままメールごと保存して問題ありません。ただし、メールシステムによっては電子帳簿保存法の「真実性」と「可視性」の要件を満たしていない場合があるため、利用前に機能や運用体制を必ず確認しましょう。 - メール内容をPDFファイルなどに変換して保存する
メールシステムが要件を満たさない場合は、メール本文をPDFやスクリーンショットに変換して保存します。印刷機能から電子化できるサービスも多く、手軽に対応が可能です。保存する際は、ファイル名に「取引年月日」「取引先」「取引金額」を含め、検索性を確保しましょう。
3. メールで受け取った請求書を保存するときの注意点
請求書の保存では、紙と電子データが重複して届く場合や、添付ファイルと本文の両方に請求内容がある場合など、状況に応じて適切に判断・管理することが重要です。ここからは、メールで受け取った請求書を保存するときに注意すべきポイントを解説します。
3-1. 紙と電子データの双方で請求書が来る場合は正本を取り決めておく
取引先によっては、同じ請求書が紙と電子データの両方で届くことがあります。この場合、紙と電子データのどちらを「正本(原本)」として保存するのかをあらかじめ決めておくことが大切です。紙の請求書を正本とする場合は紙の原本を保存し、電子データを正本とする場合は、電子帳簿保存法に基づき電子データのまま保存します。
紙と電子データのどちらを正とするかを定めておかないと、重複保存や誤った破棄につながる恐れがあります。社内の事務処理規程などで統一したルールを設け、全社員で共有しておきましょう。
3-2. 添付ファイルと本文の双方で請求書が来る場合は添付データを保存する
メールの本文にも請求内容が記載され、さらにPDFなどの請求書ファイルが添付されているケースもあります。このような場合は、本文と添付ファイルの両方を保存対象とする必要はありません。
電子帳簿保存法では、添付データを保存すれば十分とされています。添付データのほうが正式な証憑として扱いやすく、真実性や可視性を確保しやすいためです。メール本文の取引内容は参照用とし、添付ファイルにタイムスタンプを付与した上で電子データとして保存しましょう。
3-3. メールで受け取った請求書は電子データのまま保存する
電子帳簿保存法では、電子取引によって受け取った請求書や領収書などは「電子データのまま保存する」ことが義務付けられています。つまり、メールに添付されたPDF請求書を紙に印刷して保存するだけでは要件を満たしません。
電子取引保存の義務は、法人・個人事業主を問わずすべての事業者が対象です。保存期間は法人で原則7年(最長10年)と定められているため、適切なシステムを利用して長期保管に備えましょう。
まとめ
メールで受け取った請求書は、電子帳簿保存法における「電子取引」に該当し、真実性と可視性を確保した上で電子データとして保存する必要があります。紙に印刷して保管するだけでは法的要件を満たさないため、タイムスタンプの付与や事務処理規程の運用など、適切な保存方法を取ることが重要です。
そのため、社内で請求書の受領方法や保存ルールを共有し、全社員が電子データを正しく管理できる体制を整えましょう。適切な運用を行うことで、法令遵守だけでなく、業務効率化やペーパーレス化の推進にもつながります。