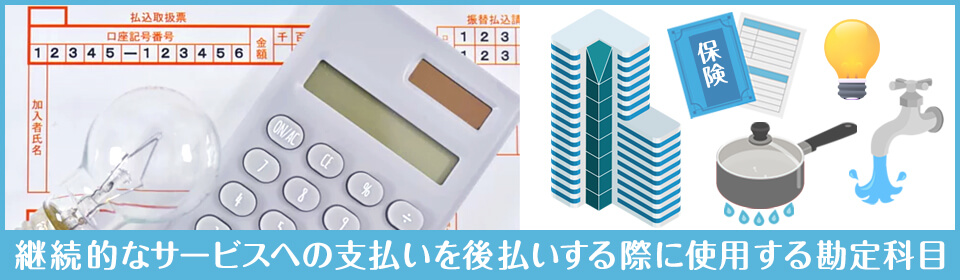コラム
未払金と未払費用の違いとは?仕訳例とともにわかりやすく解説
未払金と未払費用は、いずれも負債に分類される勘定科目ですが、それぞれの適用範囲や計上の目的には違いがあります。特に、普段の経理業務で誤った仕訳を行うと財務諸表の正確性を損ねる恐れがあるため、注意が必要です。
この記事では、未払金・未払費用の両者の定義や使い分けのポイント、正しい仕訳を行うための具体例についてをわかりやすく解説します。よく似た「買掛金」や「長期未払金」との相違点についても説明しているため、ぜひ参考にしてください。
1.未払金と未払費用の違いとは
未払金と未払費用は、どちらも「支払うべき金銭をまだ支払っていない状態」を指し、いずれも貸借対照表においては「負債」にあたります。
ただし、未払金と未払費用には上記のような共通点がありますが、企業における会計では明確に区別されることに注意が必要です。未払金は主に単発的な取引で発生した債務を、未払費用は継続的な取引で発生した債務を後払いする場合に用いる勘定科目である点に留意しましょう。
ここでは、未払金と未払費用の違いについてわかりやすく解説します。それぞれの勘定科目に該当する費用の具体的な例も併せて確認し、経理業務を適切に行えるよう理解を深めましょう。
1-1.未払金とは
未払金とは、通常の営業活動以外で発生した単発的な取引で生じた債務の未払い分が対象となる勘定科目のことです。商品や原材料の仕入れといった営業取引以外で生じた費用を後払いする場合に計上する科目です。
多くの法人では会計処理に「発生主義」を採用しており、取引が発生した時点で対価となる費用が発生することとなります。例えば「事務で使用するペンを購入した」という取引が発生した場合、取引が発生した時点で会計処理を行います。ペンの代金を後払いする場合、取引発生時点では支払いが完了していないため、「未払金」として処理することになります。
未払金として計上する費用の具体的な例としては、事務用品や備品類といった消耗品費、工具や器具の購入費をショッピングローンなどで後払いするケースが挙げられます。外注費や固定資産の未払い分も未払金計上することを押さえておきましょう。また、当期中に取引が成立しているものの、支払いが来期になる場合にも用います。
1-2.未払費用とは
未払費用とは、一定の契約にしたがって継続的にサービスや役務の提供を受けており、期日時点で対価となる費用の支払いが終わっていないものを計上するための勘定科目です。
未払費用として計上する費用の例として、従業員の給与や土地の賃借料、家賃、車や設備のリース料、保険料、借入金の利息、毎月の水道光熱費などの未払い分が挙げられます。給与計算が20日締め・月末払いであり、会計の期末が月末である企業を例に、未払費用について具体的に考えてみましょう。
この企業の場合、当月21日から翌月20日までの期間の給与が翌月末に支払われます。しかし、当月21日から当月末までの期間も役務提供を受けており、給与分の費用が当月中に発生していることに注意が必要です。したがって、月末の会計処理において、当月21日から当月末までの給与分を未払費用として計上します。
このように、「未払費用」は継続的に提供されるサービス・役務の対価となる費用の支払いが期末をまたぐ場合に使用されます。実務においては、期末に請求書が到着しておらず、債務の金額が確定しないものに使用される場合もあることを押さえておきましょう。
2.未払金・未払費用と混同されやすい科目
貸借対照表において「負債」にあたる勘定科目は、未払金・未払費用のほかに「買掛金」や「長期未払金」があることに注意が必要です。これらの科目は混同して認識されやすいため、会計処理を行う際は注意して仕訳を行うようにしましょう。ここでは、未払金や未払費用と買掛金、長期未払金の違いについて解説します。
2-1.買掛金とは
買掛金とは、商品や原材料の仕入れなど、主に通常の営業活動における掛取引で発生した債務が対象となる勘定科目です。経理における業務の負担軽減・効率化を目的として、取引先から仕入れた商品や原材料の代金を後払いする場合に使用される科目であることを押さえておきましょう。
買掛金と未払金は「対価となる費用をまだ支払っていない状態」という点では同じです。しかし、買掛金は仕入れの際に発生する債務である一方、未払金は仕入れ以外の取引で発生する債務である点が大きく異なります。また、未払費用は継続的な契約で発生する費用を後払いする際に計上する科目であり、買掛金にも未払金にもあたらないことに注意しましょう。
2-2.長期未払金とは
長期未払金とは、営業取引以外で発生した取引について、債務が決定しているものの、支払期日が決算日の翌日から1年後以降である費用を計上する際に使用する勘定科目です。社用車のローンなど1年以上にわたり分割(割賦)で支払うものや、1年以上支払いが停滞している債務などに使用することを押さえておきましょう。
長期未払金と未払金との大きな違いは「支払い完了までの期間が短いか長いか」という点にあります。決算の翌日から1年以内に支払う流動負債は「未払金」、1年を超える固定負債は「長期未払金」として処理しましょう。
3.未払金と未払費用の仕訳例
未払金や未払費用の会計処理を行う場合、取引が発生した時点と支払いを行った時点の2回で仕訳処理が必要となることに注意が必要です。ここでは、未払金と未払費用の仕訳方法について、具体例を用いて解説します。
3-1.未払金の仕訳
未払金は「負債」の勘定科目にあたるため、未払金が増えたときは「貸方」に勘定科目と金額を記載します。具体的な例と併せて仕訳の方法を確認しましょう。
【例1】1万円のオフィスチェアを後払いで購入した
事務所で使用するオフィスチェアを購入した場合、未払金(負債)が増えたとして処理します。貸方科目に「未払金」、貸方金額に「10,000円」と記入しましょう。支払金額が10万円未満なので借方科目は消耗品費として経費計上し、借方金額にも「10,000円」と記入します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 10,000円 | 未払金 | 10,000円 |
【例2】1つ200円のバインダーを後払いで500個購入した(合計10万円)
貸方の科目に「未払金」、金額に「100,000円」を記入します。購入費用の合計額が10万円となっていますが、バインダー1つあたりの価格が200円と少額であるため、消耗品費として経費を計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 100,000円 | 未払金 | 100,000円 |
【例3】10万円のパソコンを後払いで購入した
貸方の科目に「未払金」、金額に「100,000円」を記入してください。一式または一組の金額が10万円以上のものは資産として計上するため、10万円のパソコンは資産処理します。「器具備品」などとして借方に記載しましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 100,000円 | 未払金 | 100,000円 |
また、未払金を支払う場合は負債が減るので「借方」に科目と金額を記載し消し込みの処理を行います。例えば、【例1】のオフィスチェアの購入代金を、後日普通預金から支払った場合の仕訳は次のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 10,000円 | 普通預金 | 110,000円 |
3-2.未払費用の仕訳
未払費用は「負債」の勘定科目にあたるため、未払費用が増えたときは「貸方」に勘定科目と金額を記載します。具体的な仕訳例を見ながら帳簿への計上方法を確認しておきましょう。
【例1】家賃20万円を後払いした
貸方の科目に「未払費用」、金額に「200,000円」と記入しましょう。借方の勘定科目には「地代家賃」を記入します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 200,000円 | 未払費用 | 200,000円 |
【例2】未払の保険料12万円を未払費用に計上した
貸方の科目に「未払費用」、金額に「120,000円」を記入します。借方の勘定科目には「保険料」を記入するとよいでしょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 保険料 | 120,000円 | 未払費用 | 120,000円 |
未払費用を翌期に支払う場合は、翌期首に振り戻した上で支払いの処理を行います。【例1】の家賃20万円の未払費用を翌期首で振り戻し、翌期中に普通預金から支払う場合の仕訳は次のようになります。
◆翌期首での振り戻し
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払費用 | 200,000円 | 地代家賃 | 200,000円 |
◆普通預金からの支払い
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 |
まとめ
未払金と未払費用の区別は、単発的な取引か継続的な取引かによって異なります。事務用品や備品類といった消耗品や固定資産を一括後払いで購入したのであれば未払金として計上されます。対して、従業員の給与や土地の賃借料、家賃などの継続的に支払う費用は未払費用として計上するのが適切です。
また、期末における振り戻しや翌期への支払い処理を正しく理解することで、科目残高のズレや二重計上などのトラブルを防ぐのも大切です。