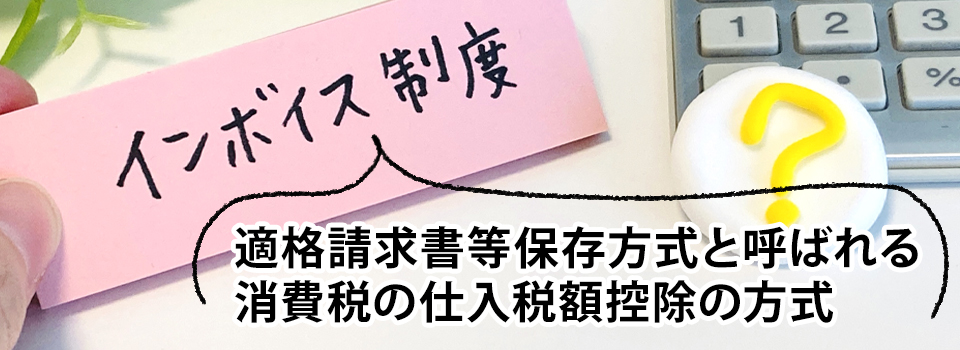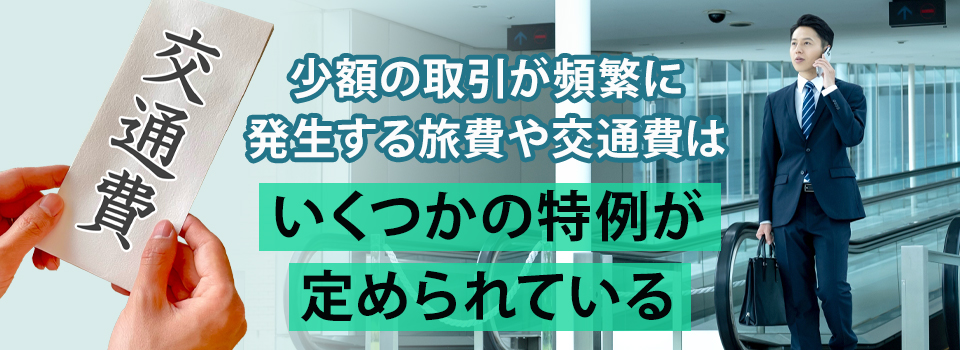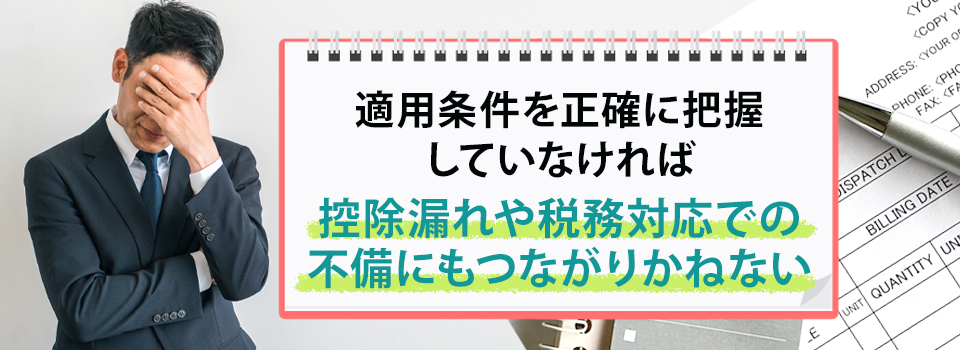コラム
出張旅費の特例に駐車場代は含まれる?インボイスの交通費を解説
2023年10月に導入されたインボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が求められます。経理業務においては、従業員の立替経費や出張旅費・交通費の処理でもこの制度が大きく関わってきます。
しかし、すべての取引でインボイスが必要になるわけではありません。少額の交通費や出張旅費などについては、特例的にインボイスの保存が免除されるケースが定められています。
この記事では、インボイス制度の基本ルールから出張旅費・交通費に関連する特例の内容、見落としがちな注意点を解説します。
1. インボイス制度の基本となるルール
インボイス制度は、2023年10月に始まった、適格請求書等保存方式と呼ばれる消費税の仕入税額控除の方式です。買い手が消費税額を控除するためには、売り手から交付される「適格請求書(インボイス)」を保存することが求められます。
インボイスを発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」に限られます。適格請求書発行事業者は、課税事業者として消費税を納める義務を負っており、請求書に必要な記載事項を明記した上で交付し、写しを保管する必要があります。
一方で、買い手側が仕入税額控除を受けるには、取引先がインボイス発行事業者であるかを確認した上で、交付されたインボイスを正しく保存しなければなりません。
また、経理部門に限らず、従業員が立替えた経費に対してもインボイス制度が関係するため、経費精算の際に領収書や請求書の宛名や発行元の確認が必要になります。取引先が免税事業者であった場合などは控除対象外となるため、会計処理にあたっては確認作業も重要です。
2. インボイス制度の出張旅費・交通費に関連する特例規定
ただし、インボイス制度では少額の取引が頻繁に発生する旅費や交通費については、経理業務の煩雑さを減らすためにいくつかの特例が定められています。
以下のような旅費交通費にかかわる特例の範囲内の費用については、インボイスの保存が不要になります。
2-1. 税込3万円未満の公共交通機関の交通費はインボイスが免除される
公共交通機関の運賃については、「税込3万円未満」の場合に限り、インボイスの保存義務が免除される特例が設けられています。これは「公共交通機関特例」と呼ばれ、鉄道・バス・モノレール・船舶などを対象としています。
特例が適用されるのは、1回の取引における税込金額が3万円未満の場合であり、月ごとの合算や複数の切符を合計した金額では判定されません。
なお、特急料金や寝台料金などは対象に含まれますが、入場料や手荷物料金などは含まれないため注意が必要です。また、同行者分をまとめて支払った結果、3万円を超えた場合も特例は適用されません。
消費税法上はインボイスが不要であっても、法人税法では経費処理のために出張旅費精算書などの書類の保存が求められる場合があります。したがって、支払目的や金額の妥当性を示す資料を整えておくことが重要です。
2-2. 必要と認められる範囲の出張旅費はインボイスが免除される
出張旅費に関しては、「通常必要であると認められる範囲の金額」であれば、インボイスの保存が免除される「出張旅費特例」が適用されます。これには、日当・宿泊費・通勤手当など、あらかじめ各企業が定めている出張旅費規程に基づいて支給される定額の手当が対象です。
この特例は、概算払い・実費精算といった支給形式を問わず、通常必要な金額であれば適用可能です。
ただし、出張旅費のうち通常必要な金額を超える部分は、給与として扱われるため仕入税額控除の対象外となります。通常必要な金額の範囲については、以下の基準で税務署が判断します。
- その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
- その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
引用:国税庁「出張旅費、宿泊費、日当等 Q107」引用日2025/6/9
2-3. 税込1万円未満の取引はインボイスが免除される
インボイス制度においては、「少額特例」と呼ばれる経過措置が設けられています。これは、特定の条件を満たす事業者が税込1万円未満の課税仕入れを行った場合、インボイスの保存なしで仕入税額控除を受けることを認めるというものです。
対象となるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者です。
少額特例の対象となる取引は、出張旅費などに限定されるものではなく、国内におけるすべての課税仕入れが含まれます。また、適用には、取引の内容や日付、金額、相手先名などを記載した帳簿の保存が必要です。
なお、この特例は時限的な措置であり、2023年10月1日から2029年9月30日までの取引に限り適用されます。期間をすぎた取引には、たとえ金額が少額であっても原則通りインボイスの保存が必要です。
2-4. 税込3万円未満の自動販売機での取引はインボイスが免除される
インボイス制度では、「自動販売機特例」が設けられており、税込3万円未満の自動販売機等による取引については、インボイスの交付および保存が免除されます。
対象となるのは「機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡が完結する取引」です。例としては、以下が該当します。
- 飲食料品を販売する自動販売機
- コインロッカー
- コインランドリー
- 金融機関のATMによる手数料付きサービス
3. インボイス制度の出張旅費・交通費で勘違いしやすいポイント
インボイス制度の特例は便利です。ただし、特例の範囲は限定されているため、誤って特例に該当しない取引でインボイスを保存しなかった場合、消費税の控除が認められなくなるおそれがあります。
特に、以下のようなポイントは勘違いしやすいため注意しましょう。
3-1. 駐車場代やタクシー代は公共交通機関特例に含まれない
インボイス制度において、3万円未満の公共交通料金についてはインボイスの保存が免除されます。しかし、この特例はバス・電車・新幹線・モノレールなどの公共交通機関に限定されており、月極駐車場代や、タクシー代・飛行機代などの公共でない交通機関の交通費は含まれません。
そのため、駐車場代やタクシー代については、支払先が適格請求書発行事業者であるかを確認し、該当する場合にはインボイスの保存が必要です。
3-2. コインパーキング代やETC代は自動販売機特例に含まれない
自動販売機特例は、税込3万円未満の取引で、機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡が完結する場合に限り、インボイスの保存を免除する制度です。しかし、コインパーキングやETCの利用はこの要件に該当しません。
コインパーキングでは代金の精算は機械で行われるものの、駐車というサービスの提供は別途行われるため、特例の対象外です。ETCの利用についても、インボイスの代替として各高速道路会社のWebサイトから取得した利用証明書とクレジットカード明細を併せて保存することで対応する必要があります。
3-3. 会社が支払ったと見なされる旅費や宿泊費はインボイスが必要になる
出張旅費等特例では、従業員に支給する日当や定額の出張手当など「通常必要と認められる範囲」の費用であれば、インボイスの保存は不要とされています。一方で、実質的に会社が支払ったと見なされるような、実費精算される旅費や宿泊費については、原則としてインボイスの保存が必要です。
特に以下のような場合は、他の一般的な仕入れと同様にインボイスの保存が求められます。
- 会社が宿泊費を直接ホテルに支払った場合
- 従業員が会社名義のクレジットカードで決済した場合
この場合は、通常必要な範囲であっても帳簿だけでは仕入税額控除が認められません。
3-4. 立替精算した場合は会社宛てのインボイスが必要になる
従業員が業務に必要な費用を立替え、後日会社に精算する場合、会社が仕入税額控除を受けるには原則として「会社宛てのインボイス」が必要です。インボイスの宛名が従業員名であった場合でも、立替金精算書を従業員が作成し、インボイスと併せて保存することで控除の対象になります。
ただし、3万円未満の公共交通機関による運賃については「公共交通機関特例」が適用されるため、帳簿に特例の旨を記載すればインボイスは不要です。
まとめ
インボイス制度では、原則として仕入税額控除のために「適格請求書」の保存が必要ですが、出張旅費や交通費など、実務上インボイスの取得が難しい取引には特例が設けられています。公共交通機関による3万円未満の運賃や、社内規程に基づく日当・宿泊費などは、インボイスの保存が免除されるケースに該当します。
一方で、タクシー代・駐車場代・ETC利用料などは特例の対象外であるため、原則としてインボイスの取得と保存が求められます。こうした点を正しく理解しておくことが、経理上のリスクを回避するために重要です。
制度上の特例は便利ではあるものの、適用条件を正確に把握していなければ控除漏れや税務対応での不備にもつながりかねません。インボイス制度の特例規定を正しく活用し、実務に即した処理を心がけましょう。